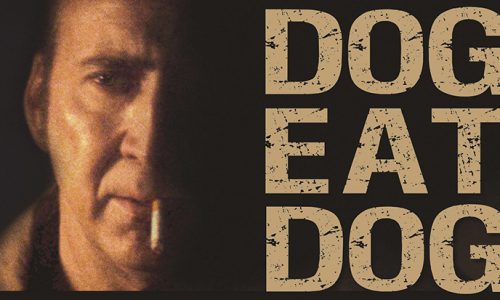(1989年 監:メアリー・ランバート 出:デイル・ミッドキフ、フレッド・グウィン)
Sometimes, dead is better.
家族と共にメイン州の片田舎へと引っ越してきたルイス・クリード。だが家の庭から延びる細道の先には、地元の子供たちによって造られた「ペット霊園」があり、その更に奥には、先住民が死者の埋葬に使っていた「禁断の土地」があった。そこに亡骸を埋葬すれば、死んだ者に新たな命が宿り、甦るというのだ。ただし生前の魂とは全く異質の「何か」によって操られる異形のモノとして。悲劇的な交通事故により幼い息子・ゲージが命を落とした時、ルイスの胸中にある恐ろしい考えが生まれる……。
中学生の頃、スティーヴン・キングの原作本にどハマリしていた中で、ビデオジャケットのおどろおどろしさに惹かれて誕生日プレゼントにねだったのが本作だった。確かにホラー映画には違いなかったが、観終わって感じたのは、恐怖よりもむしろ言いようのない悲愴感。ラモーンズによる悪名高き主題歌「ペット・セメタリー」※(観た人なら誰もが感じるはずだが、恐ろしいほど本編とミスマッチな曲なのだ)も、虚脱した観客にせめてカラ元気でも注入してやろうという製作側の心遣いだったのではないかとさえ思えてくる。
本作に否定的な意見として「主人公に学習能力が無さすぎる」というものがある。彼の行動が引き起こした事態を思い返してみれば確かに一理あるのだが、しかしそれこそが人間の性というものだろう。劇中の台詞としても、キャッチコピーとしても使われた言葉“Sometimes, dead is better.”(「時には、死の方がいい」)は、悲嘆に暮れるルイスの前では効力を失ってしまう。恐ろしい結果が待っていると分かっていても、愛情があるからこそ呪われた力までも借りようとする。もしも「禁断の土地」が実在していたら、邪悪な誘惑をはねのけることができる人間はむしろ少数派なのではなかろうか……そんな考えも頭をよぎるのだ。特にゲージを演じるミコ・ヒューズがまさに「天使のような」という形容がピッタリなほど愛くるしいので、説得力の強度はかなりのものである。
キング原作の映像化作品には駄作も少なからず存在するのだが(原作者自身がメガホンを取った『地獄のデビル・トラック』なる珍作まである)、本作は小説から映画への換骨奪胎の成功例と言える。ゴア描写は比較的少ないが、ピンポイントで強烈な痛覚刺激シーンも転がっているので、心構えをしたうえでの鑑賞がオススメである。内容云々以前のレベルでトラウマだけ植え付けてしまったのではモトも子もないので、どうかその点だけはご注意されたし!